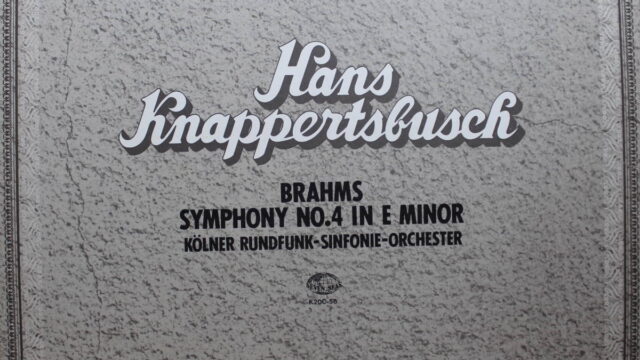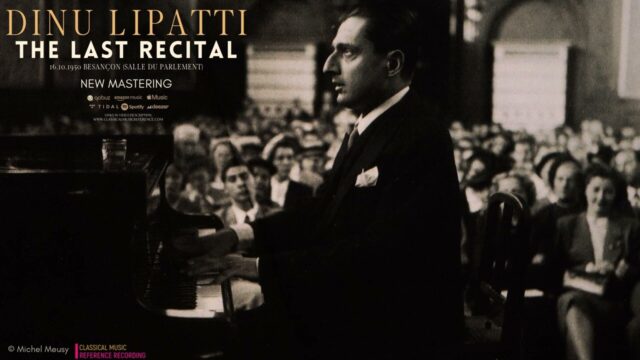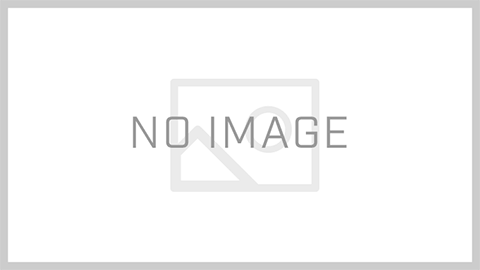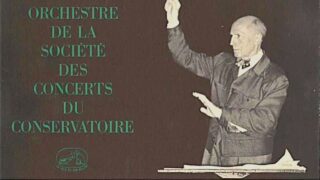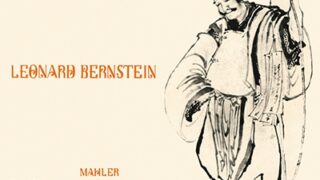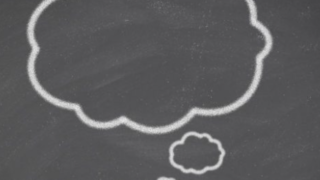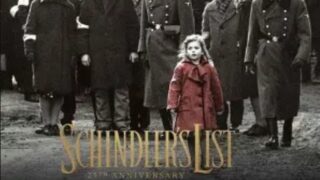1990年代、ブルックナーといえばチェリビダッケ、ヴァントか日本人指揮者であれば朝比奈が鉄板という時代。当時だったら若杉弘とNHK交響楽団によるブルックナー交響曲全集発売!といっても、大学生でミーハーな私がすぐに手に取ることは無かったかもしれません。若杉弘といえば80年代のケルンやドレスデンでの活躍が特筆すべきキャリアです。オペラハウスでもコンサート双方で高い評価を得ながら、コネやマネージメント会社の力も通用しづらい旧東ドイツで実力と学識の高さでその地位を勝ち取ったのは、小澤征爾よりも凄いことだと今では思います。ベルリンの壁崩壊が無ければ90年代もシュターツカペレ・ドレスデンで活躍していたことでしょう。

当時は録音も少なかったことから若杉さんの音楽を聴く機会は少なかった。たまにN響を振っているのをTVで見る位。印象としてはあまり残っておらず、端正で歌心のある音楽作りをする位の認識。朝比奈に比べれば音の重心は高めでテンポも中庸で特徴に貧しく、ブルックナー向きというよりはマーラー向きという印象。そんな90年代にNHK交響楽団は録音を視野に入れながら、若杉さんと3年に渡るブルックナー交響曲ツィクルスを企画。CD発売は3番と7番でと頓挫してしまいましたが、計画は完遂。当時はなぜ朝比奈でなく若杉で?と思ったものです。
youtubeで80年代の若杉さんの映像を最近見ていると、当時の私の認識は甘かった、わかってなかっただけなんだと気づきました。弦を美しく響かせるのが巧みで、全体の流れをしっかりと作りながら細部にも配慮がされている。シュターツカペレ・ドレスデンが若杉を気に入っていたのもわかる。もっとそのコンビで録音が残されていたらなぁと思っていた矢先、今頃になってALTUSがNHKアーカイブにある録音からリマスタリングを経て全曲をCD化しました。購入にはかなり悩みましたが、これは良いCDでした。
これは素晴らしい交響曲全集で、逆に朝比奈のCDはほぼ棚から消えることに。朝比奈隆ほどの音楽の巨さは無い。しかしやはり大阪フィルとN響とのオーケストラの差は大きく、また意外と若杉さんのブルックナーへの適正もよい。思ったよりもテンポは遅めで粘るところは朝比奈よりも粘る、ここぞといった時の歌いこみや低音の抉りなど期待を遥かの超えたもので、録音もFM的ではあるものの非常に良い。短いスパンで同じホール(サントリーホール)で行ったライブのため、表現と響きに統一感がある。リハーサルでも同会場を使用して行うという徹底した準備がその根底にもあるのでしょう。
ブルックナーの交響曲全集というとどうしても前期曲の感銘度が落ちるもの。しかし不思議とこの全集ではそれを感じさせない。どう考えても旋律・作曲技法・オーケストレーションで劣るはずの1・2番ですら、6・7番と同じくらいの満足度というか重みが感じられるのが不思議。各曲テンポは中庸から少し遅めで進めながら、聴かせどころやフィナーレなど音数が多いところではぐっとテンポを落としオケを鳴らしきる。弦の歌わせ方はやはりうまく、ドイツのオケ?と思わすようなうっとりする部分もある。ピチカートは強めに弾かせていて通常聴こえないところも明晰に聴こえる。
音量も弱く演奏させ過ぎないようにして痩せさせない、フォルテも力ませないので音が濁らない。金管・木管は比較的大きめで吹かせている。当時のN響のブラスは今よりも多少音が硬めで気になりますが、これはいかにもライブっぽい。正直アンサンブルの縦線が合わないところは散見されるものの、すっと帳尻を合わせて元に戻す巧さは若杉の歌劇場仕込みならでは。無いものねだりとわかっていながら、「これがシュターツカペレ・ドレスデンだったら・・・ティンパニがゾンダーマンでホルンがペーター・ダムで録音がシャルプラッテンだったら長きに渡り評価されただろうに」と思わずにはいられない。
これは89年なので全集とは別演奏の第9。ティンパニがやたらうまいと思って聴いていたら、ゾンダーマンでした。
相当若杉自身も気合が入っていたようで時折「う”っ」など力こぶを入れる指揮者の声が聴こえます。インバルやコバケンのような耳障りなものでなく、いかにもライブ録音で聴いているこちらにも自然に一緒に力が入る部分で邪魔な音ではありません。全体的に今どきの「スタジオ録音並みのライブ録音」ではなく、いかにも一発録り・一期一会的な緊張感と空気感が感じられる名ライブ録音。1年目に比べると3年目にはオケと指揮者相互の呼吸が合致し、ホールの特徴もつかみつつ解釈もこなれ、また観客の反応も高まっていくのが感じ取れる。
1年目:3番・7番・8番
2年目:2番・4番・6番
3年目:1番・5番・9番
1年目は8番、2年目は6番、3年目はやはり9番が気迫・演奏ともに素晴らしい。特に6番は特筆すべき名演で、この曲にしては演奏後の観客の反応がいい。第4楽章コーダ最後の猛烈なテンポダウンはクレンペラーの演奏でも同解釈があるように、比較的軽いと言われる6番の印象を大きく変えてくれる名解釈。
よくよく考えると若杉さんは朝比奈隆とは当然面識があるでしょうし、ドイツでもヴァントやチェリビダッケのオーケストラとも共演し、両指揮者とも付き合いもあった。そのいいとこどりをしたかの様な演奏とも言えます。朝比奈よりオケを歌わすことは1枚上、ヴァントほど詰めがきつくなく、チェリビダッケほど神経質でも粘着質にテンポが遅くない。テンポは変化させるが音楽が軽くならないように早くはしない。歌いたいところで朝比奈やチェリ位テンポを遅くするときもあるが、テンポを戻す際にも急に舵を切らず、「早くしますが後で元に戻します」という印象を与えない。
若杉さんとシュターツカペレ・ドレスデンが絶対好きになってしまう映像。
これほどいい全集にもかかわらず、たいして話題にもならないのは勿体ない。本当に残念なクラシック音楽事情とCD不況です。最近のブルックナー演奏、ゲルギエフはやはり肌に合わないし、ティーレマンは昔とあまり大差ないし、ネルソンスを聴くと昔のゲヴァントハウスは・・・といいたくなるしと不満を感じている方に是非一度聴いていただきたい全集です。
SACDの方が安いという不思議。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。

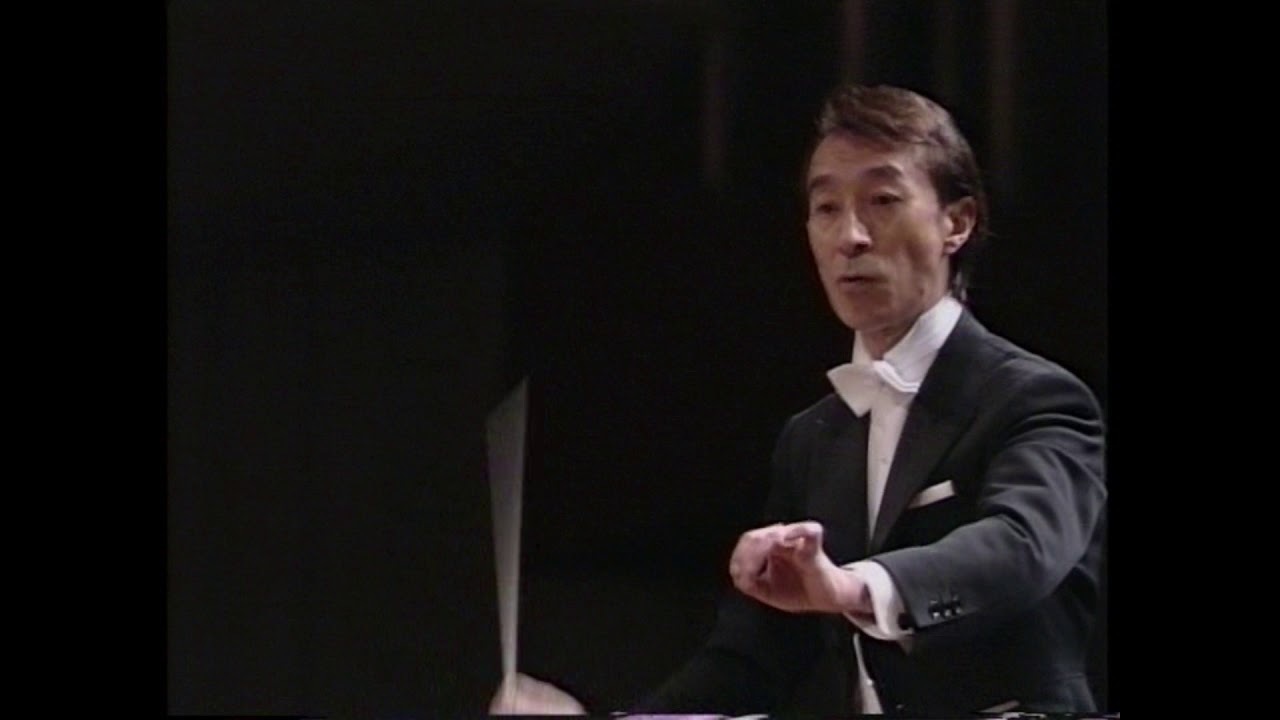
![ブルックナー : 交響曲全集 / 若杉弘、NHK交響楽団 (BRUCKNER : COMPLETE SYMPHONIES / Hiroshi Wakasugi & NHK Symphony Orchestra, Tokyo) [10CD] [日本語帯・解説付] [国内プレス] [Live]](https://m.media-amazon.com/images/I/41d0xDUS-OL._SL500_.jpg)
![ブルックナー : 交響曲全集 / 若杉弘、NHK交響楽団 (BRUCKNER COMPLETE SYMPHONIES / Hiroshi Wakasugi, NHK Symphony Orchestra) [3SACDシングルレイヤー] [国内プレス] [日本語帯・解説付] [Live]](https://m.media-amazon.com/images/I/61+kb+0nHuL._SL500_.jpg)